ぢきゅうぢそく
メイン:1号、サブ:雪
コミュニケーションイベント
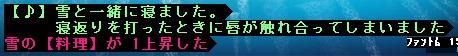
「ごちそうさまでした」ってことなのかな??
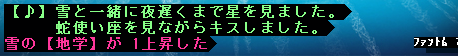
地学と天文はセットであります
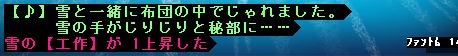
えーと、これは……
テクニック→器用→工作 とか
開発→工作 とか、そういう流れなのかしら
いや、まだ開発ではありませんよね、この段階では
◇
以下、3つ目のイベントの妄想文です
前置きが長めですが、結局いちゃいちゃです
(※ 2つ目の星を見たイベントの妄想小話も書いてます
よろしければあわせてどうぞ →異ぢきゅう1雪pre)
◇
雪とこの無人島で暮らすことになってから随分歳月が流れた。
以前も月や地球塔で二人きりで過ごした事はあったが、今回ほど長くはなかった。この島での暮らしは、もう500日を軽く超えていた。
それこそ最初は体一つで放り出されて、衣食住に困窮する状況だった。
どうにか二人で協力して、使えそうなものを集めて食いつなぎ、道具や家屋を作り、サバイバルを続けるうちになんとか生活は安定してきた。
ぐるりと海で囲まれた島を歩き回り、他の人間を探した。
未だ島の全てを探索出来てはいないが、今のところ自分たち以外の人間には出会えていない。いるのは虫や獣ばかりだ。
アケローンの河から落ちた時のように、ワームホールや転移装置を使った際に何らかの事故で飛ばされた可能性も考えた……これはオレの考えではなく雪の推測なのだが。
地球か月か、関連する星系か、思い当たる場所を列挙する。
島の環境を観察し、星々を見上げ、文明の痕跡を探し、必死に現状を把握しようとした。
ここまでの流れは月での探索と基本的に一緒だ。
だが今は、残念ながら雪とオレの知る土地、世界と結びつかない。
時空の迷子となっていた。
なかなか終りが見えない。
でもまだこの島の全てを調べたわけじゃない。
手筈を整えて海に出るという手段もある。
希望を捨てずに、地道に日々探索を続けていた。
この暮らしを続けていられるのは……苦しくて諦めたり投げ出したりせずにいられるのは――――
オレはここでの暮らしが楽しくなってきていた。
幸いにしてこの島は物資が豊富だ。
慣れれば余裕を持って暮らすことが出来る。
気候も穏やかで常春か、常夏か、その間ぐらいといったところだ。
時々荒れる日もあるが、荒廃した地球や閉じ込められていた研究所と比べれば楽園のようだった。
ルイン達とはぐれてしまい彼らのことが気になってはいたものの……徐々にその思いは薄れて、追い詰められて戦う日々から解放されて、心が楽になってしまっていた。
何より大きかったのは雪の存在だ。
自分一人だったら生き延びることは出来ても、決して幸せではなかっただろう。
この島に来た時、雪はペガサスの姿だった。
浅からぬ因縁があり、そしてまた長く一緒に戦ってきた大切な仲間だ。
たとえ獣の姿をしていても、その赤い瞳と顔付きを見ればすぐに雪だと分かった。
そして雪は人の言葉を話すことが出来たのだ。
地球塔でペガサスに変異してから、雪はベガのように人語を話すことは無かった、出来ないのだと思っていた――実際できなかったのだろう。
ところがこの島では話せるのだ。
嬉しかった。
話すことが出来なくても、獣の姿でも、雪と一緒にいるだけで心強かったのに(オレはペガサスの雪をとても気に入っていたから、というのもあるのだが。強くて凛々しくて格好いい、それに優しい)、雪と話せるんだ。
普段は落ち着いていて、でも時々怒ったり悪態をついたり喧嘩をしたり、そんなことが嬉しくてしょうがなかった。
時には探索しながらふざけたり遊んだりもした。
言語による意思の疎通の重要性も痛感していた。
生活を軌道に乗せるまでそう長く掛からなかったのは雪の知識のお影で、最初から共有していられたのだから。
更に不思議な幸運は続いた。
ある日、雪が人間の姿に戻ったのだ。
昔から見ていた、オレが一番良く知っている雪の姿、変異する前と何一つ変わらない。
雪もオレも驚きながら喜んだ。
この変化は雪にとってとても大きなことだったようだ。
人間に戻ってから殊更に、毎日機嫌が良い。
些細な喧嘩はしょっちゅうの事だったが、二人きりで暮らすうちにオレ達は随分仲が良くなっていった。
雪がまだペガサスの姿だった頃、家具を作りそれぞれの寝床が調ってからも、地球塔でしていたようにオレはよく雪の体に寄りかかって眠った。
雪はどういう心境だったんだろう、嫌がらず一晩一緒に居させてくれた。
少し肌寒い夜に身体を預けると温もって安心した。
艶やかな純白の毛並みがすべすべと肌に当たって、心地よく眠れた。
雪が人間に戻ってからも、オレは一緒に寝ようとした。
なんとなくそうしたくなる時があるのだ。
月で雪と野宿していたことはある、けれど今は違う。
肩を並べて隣で眠りたい。
横になって寝入ろうとする彼の傍らに膝をついて求めると、雪は暫し迷った顔を見せた後に……端に寄って寝床を半分開けてくれた。
オレは機嫌よく潜り込んた。
二人で寝るには狭くて肩や腕がぶつかって、温かくて嬉しくて、感じたことや喜びを全て口にした。
雪は適当に相槌を打ちながら微睡んで、程なくして静な寝息が聞こえ出した。
オレも幸せな気分のまま、とろとろと眠りに落ちていった。
時折そんなことを繰り返していたある日。
その晩もオレは雪の寝床に潜り込んでいた。
すぐには眠らずに二人してふざけてじゃれているうちに、どちらからともなく唇が重なった。顔が熱くなる。
「二度目だな、キスするの」
オレの言葉に、雪は「おや?」とでも言うように眉を上げて、若干嘲るように笑った。
「三度目だろ」
「え? ……この前星を見た時が初めてで、今で二度目じゃないか?」
「その前! 俺が寝てる時にキスしてきただろ」
「あっ…………気付いてたのか……」
「俺の職業は?」
「軍人……特殊部隊所属だったな」
「正解、気配で気付くっての。それになあ、てめえの体重考えろ!
ちょっと身体がぶつかっただけでもそれなりに衝撃なんだぜ」
気付いていたならばと、雪には正直に打ち明けることにした。
「あの時は寝返りを打ったらぶつかってしまったんだ……」
また雪は眉をぴくりと動かして笑う。
「なあんだ、ワザとじゃなかったのか、そーかそーか」
思わず雪の肩を掴んでぐっと詰め寄る。
「わざとの方が良かったのか?」
「さあてね」
「雪は何も言わなかった、怒らなかった」
「眠くて面倒だっただけだ」
愉快そうに、機嫌が良さそうに笑って答えているが、どうにものらりくらりと躱されている感じで雪の意図が読めない。
「オレはあの後一晩眠れなかった。胸がざわついて……」
「そりゃあ寝不足になっただろうなあ」
雪の受け答えに焦れったくなって語調が強くなった。
「今はわざとしてる! 雪とこうしたいからしてるんだ。雪はどうなんだ?!」
怒りとは違うが、答えが欲しくて堪えられない。
きっと今のオレは険しい顔をしているんだろう。
「フッ………クッ…アッハハハッ………ったく不思議な奴だよおまえは……
ってそうか、1号、おまえは人間でもなけりゃ完全に作り物の怪生物でもねえ、
中途半端の出来損ないだもんな、そりゃあおかしいよな」
笑われて変に気が抜ける。
雪のこんな言いようはよくあることなのでさほど気になりはしない。
けれど不可解だ、何を言いたいんだ。
「俺がこれだけ許してやってるってのにさ、鈍いにも程があるぜ。
いちいち言わなきゃ分かんねえのか?
それともワザと言わせようとしてるのか?
……いや、おまえにゃそんな芸当は出来ないか」
雪がどんどん一人で喋って、だんだん置いてけぼりにされているような気分になってきた。
もうどうでもいい、もっと雪と仲良くしたい。
再び唇を寄せようとしたら、左右の頬を挟むように両手でバチンと叩かれた。
「ッ……!」
そのまま顔を掴まれ動きを止められる。
「雪、何を……」
「おまえさ、長いことここで俺と二人っきりになって……
俺しかいなくて、他に誰もいなくて、他人に飢えてんだよ。
人恋しくなってんだろ? おまえは仲間ができてその味をしめちまったんだ。
だから俺なんかを相手に変な気を起こしてるんだよ」
『俺なんか』……それはオレ達の過去の因縁を指していることに他ならない。
雪はいつだって忘れていない。勿論オレだって……
「全部じゃないけど、雪の言う通りかもしれない。雪がいるからさみしくない。
それに一緒にいるんだから、仲違いしているよりも好きで、上手くやって行けた方が良い」
「そうだな………このド正直!!!」
視線を落とし、はぁ………と溜息をひとつ零し、雪は顔を上げた。
愉しそうで少し情けなさそうな、あまり見たことのない笑顔だった。
「俺だって人のことは言えねえな。
飢えまくっていい加減目が眩んじまってるから、おまえなんかとこんな事をしてるんだ」
身を乗り出してきた雪に唇を奪われた。
嬉しくて、それが全てに思えた。
言葉も理屈もどうでも良くなった。
夢中になって何度も口づけを交わした。
途中で何度か離れて見る度に雪の顔は赤くなっていき、とても楽しかった。
キスしながら雪に身体を撫でられる。脚も絡ませてくる。
オレは雪に抱きつくくらいしか出来ないでいたが、雪はなんというか……巧い、快い。
雪の手のひらと指先がオレの肌の上を直に滑る。
肩、腕、背、胸、腰と、だんだん降りてくる。その先は……
「1号、期待してんだろ」
見透かされて、雪にクスクスと笑われた。
笑い声さえ心良くて、オレは素直に頷いてその先を求めた。